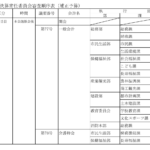■一般質問を実施しました!(令和7年第3回市議会定例会)■
本日の市議会定例会において一般質問を実施しました。
1 米の増産に向けた本市の農業政策について
国を挙げて米を増産するにあたり、インフラ面も含めた環境整備が急務ですが、今回は「特定地域づくり事業協同組合制度を活用した人手不足解消」と「耕作放棄地解消のための第3セクター設立」の2点を提案しました。実現への道を模索し、勉強を重ねたいと思います。
2 高齢者終身サポート事業について
高齢者終身サポート事業については、幸いなことに、現在の本市では身寄りのない高齢者が比較的少ないため、問題の顕在化には至っていません。しかしながら、今後の影響を考えて今から準備しておくべきであり、国及び県の動向を注視していきます。
3 健康診断のあり方について
健康診断の見直しを促すような内容は、これまで市町村議会で取り上げられた例はほとんどないものと想像されます。鈴木定幸市長には、健康診断の弊害について理解を示すご答弁をいただけましたので、私としましても調査研究を進めます。
4 東野地内の市道整備について
市道は日々の生活に直結するテーマですので、周辺の地域も含めて、引き続き皆様からの要望に耳を傾けます。そして、今後の市の対応を注視し、しっかりとフォローしていきます。
ご多忙中にもかかわらず、傍聴にお越しいただいた皆様に心から感謝申し上げます。
改めまして、地域の皆様方の思いや寄せられた期待に全力で応えられるよう努力したいと思います。
ここに一般質問の全文を掲載します。
引き続き頑張って参りますので、よろしくお願いいたします。
一般質問(令和7年第3回市議会定例会)
1 米の増産に向けた本市の農業政策について
本年6月の令和7年第2回定例会にて、私が令和の米騒動と本市の農業政策に関する一般質問を行いましたが、その後8月になり、ようやく国は米の生産調整(事実上の減反政策)に区切りをつけ、増産へとかじを切りました。
ここで重要なのは、国を挙げて米を増産するにあたり、本市としてインフラ面も含めて何が必要で、今後どのような具体策を取っていくかです。先ほど述べた本年6月の一般質問の中で、市長は次のような趣旨の答弁をされました。まずは、農地を利用する担い手の立場としてはいかに耕作条件が整っているかが大変重要であること。次に、「基盤整備事業」によるインフラ整備等、優良農地の保全管理を推進していきたいこと。つまるところ、本市の農地を良い条件での営農が可能な状態とし、担い手が積極的に耕作したいと思わせるような環境づくりが必要だということです。これは、令和の米騒動をきっかけに稲作、ひいては農業全体への関心が高まっている今こそ、検討しておくべき事項です。
そこで今回は、農業の担い手の目線で本市の農業政策を具体的に考えていきます。
(1)竹林・森林が水田に及ぼす被害への対策
先日、市内の米農家さんとお話しした際、玉川沿いの竹林・森林が水田に及ぼしている被害を耳にしました。幾つか例を挙げると、第一に、竹や木が水田に倒れてくる。第二に、水田の一部が日陰になることで米の品質・収量等が落ちる。第三に、根っこがコンクリートを侵食し水路が漏水する等の被害です。米農家さんの切実な声であり、いずれも無視できない深刻な問題と考えます。
そこで、本市において竹林・森林が水田に及ぼす被害への対策の現状について、産業観光部長にお伺いします。
産業観光部長
竹林・森林が水田に及ぼす被害への対策について、お答えいたします。
本市の稲作におきましては、地域経済や農村社会を支える基幹的な産業であることは誰もが理解しているところかと思います。また、議員ご指摘のとおり、水田に隣接する森林や竹林の繁茂による日照不足が要因での生育不良や倒木による被害のほか、落葉や枯枝の流入による管理の負担増、鳥獣被害の温床等様々な弊害があることも市としては認識しているところです。
しかしながら、森林の管理につきましては、基本的に所有者の責任において行われるものであり、自治体が個人の私有地を直接管理することはできないのが現状でございます。
市としましては、森林所有者から伐採等に関する問い合わせがあった場合には、森林法に基づき整備が適正に管理されるよう助言や指導をしておりますが、隣接農地からの苦情に対し、森林所有者へ個別の指導等は実施しておりません。
この様な状況を踏まえ、市としましては、市のホームページ等を活用しながら森林の適正管理を所有者へ広く周知してまいりたいと考えております。また、整備地区であれば、その多くは土地改良区や水利組合の受益地であることから土地改良区などとの連携も図りつつ、営農条件の改善に努めてまいります。
森林所有者への指導等、難しい点が多々あるかと思いますが、今後も営農条件の改善に取り組んでいただければ幸いです。
(2)揚水機場の老朽化対策
水田での稲作にとり、水をどのように引いてくるかは最重要事項です。本市の各地に設置されている揚水機場は、水路等からポンプを用いて取水し、地下に埋設されたパイプラインを使って田んぼに水を送るための施設です。
この揚水機場について、築30年以上が経ってポンプや送水管をその都度修理してきたが将来的な展望が見えないとの話を複数の米農家さんから伺いました。具体的な金額を申し上げれば、機場ポンプ1台でオーバーホールに約200万円、新規購入の場合には、約2千万円かかるという声もあります。
本市における揚水機場の老朽化対策についてのお考えを産業観光部長にお伺いします。
産業観光部長
揚水機場の老朽化対策について、お答えいたします。
揚水機場は水田に水を送るための用水施設であるため、その当該水田を所管する土地改良区又は水利組合が管理すべきであることから、揚水機場の更新や修繕をする場合には、管理者である土地改良区又は水利組合において徴収している賦課金を原資とし実施することになります。
しかし、ご指摘の通りポンプ等の更新・修繕には多額の費用を要することから現在も土地改良区及び水利組合と協議を行い、県単補助金、維持管理適正化事業を活用し対応をしてきているところでございます。
揚水機場の老朽化対策としましては、引き続き、通常の維持管理については賦課金による管理者の責任においてお願いすることになりますが、ポンプの更新、修繕(オーバーホール等)、パイプラインの大規模改修といったものにつきましては、関係機関と協議を行いながら、補助金等を活用して受益者の負担軽減に努められるよう対応してまいりたいと考えております。
土地改良区及び水利組合との協議を含め、引き続き受益者の負担軽減を進めていただければと思います。
(3)外国人による農地取得の現状
本年4月1日から日本に住む外国人が農地を取得する際の要件が厳しくなりました。農地取得を希望する外国人は、在留資格の期間を審査機関に報告する必要がありますが、その際、短期在留者や在留期間が不安定な場合は、農地取得が認められにくくなります。
取得後すぐに遠方へ引っ越しをしたり、実際に農業に従事しないケースを防ぐため、農業委員会が厳しく審査しますが、具体的な期間については「作物ごとに収穫期間が異なるため、事例ごとに判断する」とされています。
ところで、令和7年6月5日付茨城新聞の記事によれば、北海道ではフランスの法人が43.9ha、本県ではスリランカと中国の法人が計3.65haを取得しているほか、全国的に外国法人等による農地取得のケースが見られます。近年、外国人や外資系企業による転売や投資目的の農地取得が増加し、地方自治体や農業従事者から懸念の声が高まっている現状は決して無視できません。
私は昨年12月の令和6年第4回定例会にて、外国人による本市土地建物の所有について執行部にお伺いしました。我が国の食料安全保障を考えれば、農業においては自国民が耕作する農地の保全こそが極めて肝心ではないでしょうか。
そこで、外国人による農地取得の本市の現状について、農業委員会事務局長にお伺いします。
農業委員会事務局長
外国人による農地取得の現状について、お答えいたします。
外国人の関係する法人などが、農地を取得する事例が全国的に増えており、農地の目的外の利用などの懸念が高まっています。このことから、令和7年4月より、在留期間の確認など、外国人等が農地を取得する際の規制が強化されました。
本市の外国人等による農地取得の事例についてですが、確認できる過去の記録データから、令和7年8月末現在まで、本店の所在地が日本以外の国である外国法人又は居住地が海外にある外国人と思われる者による農地取得はなく、また、外国法人又は居住地が海外にある外国人と思われる者が、議決権を有する法人又は役員となっている法人による農地取得もありません。
食料の安定供給を図るための重要な生産基盤である農地は、農地法に基づき、その権利移動、転用等は規制されており、農業委員会からの許可が必ず必要です。
外国人による農地の取得については、農地法の許可要件を満たしていれば可能ではありますが、外国法人等の農地取得に限らず、農地の転用や売買等の農地取得については、農地法等に基づき、農業委員会として適切に判断してまいりたいと思います。
今後も農業委員会においては、農地を取得する者の国籍も含め、厳正なチェックを強く要望します。
(4)特定地域づくり事業協同組合制度を活用した人手不足解消の提案
農業において深刻な課題の一つが人材不足です。本年6月に行った一般質問の中でも触れたように、担い手の高齢化等による後継未定の農地の存在が全国的に大きな問題になっています。一方で、農業は年間を通じて常に仕事があるかというと、必ずしもそうではなく、繫忙期だけ人が必要になるというケースも多いかと思います。
そのような中で、国の「特定地域づくり事業協同組合制度」を活用し、本年1月に本県のかすみがうら市で「かすみガウガウら協同組合」が設立されました。総務省のホームページによれば、特定地域づくり事業とは、地方の人口減少地域等で、季節ごとの労働需要に応じて複数の事業者の事業に従事する、いわゆるマルチワーカーに係る労働者派遣事業を指し、令和2年に作られた新しい制度です。
まず、特定地域づくり事業協同組合、以下「組合」と呼びますが、組合の事業者側のメリットは、都道府県知事から認定を受けることで、通常は国の許可が必要な労働者派遣事業を、県への届け出のみで始めることができる点です。さらに、財政面で言えば、組合は市町村から補助を受けられます。例えば、一人あたり年間400万円で6名雇用し、事務局運営費が600万円かかるとした時、合計3,000万円が必要になりますが、このうち半分の1,500万円は市町村からの補助で、残り半分は組合員に職員を派遣した際に得られる利用料金収入で賄います。組合は実際の経費の半分を支出するだけで済みますし、先ほど述べた市町村からの補助1,500万円については、国の交付金及び特別交付税を充てる結果、実質的な市町村の負担分は事業費全体の8分の1である375万円に留まります。
次に、組合で雇用される側、農業の担い手側に目を向けると、第一に、自然環境等に左右されがちな不安定な農業の分野で、組合に属して安定的な雇用が保証されるメリットは大きいと考えます。第二に、先ほど本制度は複数の事業者の事業に従事する、いわゆるマルチワーカーの派遣事業だと申し上げましたが、年間を通じて時には稲作と畑作の両方、あるいは様々な種類の作物を育てることで、本人にとっての気づきや学びに繋がり、先輩の経営者との交流の場にもなります。
さらには、地域のメリットとしては、地方移住に興味を持つ市外・県外からの若者を呼び寄せる効果や、組合が地元の若者の就職先の一つの選択肢になること等が挙げられ、地域の活性化が期待できます。具体的な数字としては、全国に約100個ある組合のうち、全体の社員の約6割が20~30歳代で、かつ約7割は地域外からの移住者であり、さらには組合を退職しても約7割がそのまま地域に留まって定住しています。
令和7年4月8日付、同年5月16日付、同年6月5日付茨城新聞の記事によれば、かすみガウガウら協同組合は、新規就農者や移住希望者を正社員として雇い、市内の若手農家の下に派遣する仕組みです。これまでに正社員3名を採用し、季節の需要を踏まえて繫忙期ごとの雇用を組み合わせ、年間を通じて働きながら栽培技術や経営を学ぶ場を提供しているそうです。
本市の米農家さんの話では、農業も結局は人の問題に行き着くが、人を一人雇うだけの金額を稼いでいくのは至難の業であり、農業は繫忙期と閑散期の格差が激しいので、スポット的に人を派遣してくれる組合の制度は良い試みだとおっしゃっていました。さらに別の方にお話を伺ったところ、米農家はそこまで人は要らないので、閑散期に雇用しても無駄になる。問題は田植えをどのように早く済ませるかであり、農業経営者の中で希望が出てくれば、組合による派遣事業を行う価値はあるとのことでした。
猛暑の時期の草刈り要員の不足、繁忙期のトラクター等の運転手不足の問題、また、ある程度規模の大きな米農家では、田植えの時期に苗を軽トラックに積んで運搬し、田植え機にセットする一連の作業に人手不足が発生しているとのことです。
本市では既に農業の人材育成に向けて走り出している常陸大宮市農業アカデミーがありますが、これと連携する等して上手く活用できれば、安定的な雇用を創出し、なおかつ農業の担い手を育て、地域の活性化にも繋がる格好の仕組みになると思います。
そこで、特定地域づくり事業協同組合制度を活用した農業の人材不足解消の可能性について、本市のお考えを産業観光部長にお伺いします。
産業観光部長
特定地域づくり事業協同組合制度を活用した人手不足解消の提案について、お答えいたします。
議員ご指摘のとおり、本市における人手、いわゆる労働力の不足につきましては、農業分野のみならず、商工や医療、福祉など様々な分野において大変深刻な問題であると認識しているところです。
そのような社会状況の中、令和になって始まったこの制度につきましては、労働力不足を補う有効な手段の一つに成り得るものと考えております。
お示しいただきましたかすみがうら市の事例につきましては、農業分野に特化した協同組合で、全国的にも珍しい取組であり、大変参考になる事例であると認識しております。
しかしながら、国の想定ではあらゆる分野の業種が参画することで、幅広い職種から就業先を選択できれば移住希望者等にとっての魅力度向上が期待できる、としているところですので、本市につきましては、今年度、農業の担い手育成を目的に立ち上げた農業アカデミーとの兼ね合いも考慮しつつ、今後、どのような形で取り組めるのか、全庁的な展開を視野に入れて関係部署と連携しながら協議・検討してまいりたいと考えております。
まだまだなじみのない制度ですので、まずは内容の理解に努め、市のホームページ等を活用しながら制度についても広く周知してまいりたいと考えております。
今ご答弁のあったように、全庁的な展開を視野に入れて関係部署と連携しながら是非とも前向きに進めていただければ幸いです。
(5)耕作放棄地解消のための第3セクター設立の提案
①農地バンクを活用した特例事業「農地売買事業」の現状
これまでの一般質問でも触れてきたとおり、本市の農業が抱える大きな問題の一つは、耕作放棄地の問題です。耕作放棄地化を防ぐためには、やはり担い手に好まれるような農地を整える必要があり、その手段の一つが「基盤整備事業」です。
基盤整備事業とは、農業生産の基盤となる農地や農業用水、農業用道路などの整備を行う事業の総称です。具体的には、農地の区画整理、水路や排水路の整備、農道の整備などを行い、農業の効率化や生産性向上、農村の環境保全などを目的とします。
基盤整備事業によって農地の集約化を進める上でネックになる最大の点は、新たに農地を継承した人、特に農業と無縁な人にとって、お金が欲しいのであって土地は不要だというケースが極めて多いことです。多くの場合、不要な土地を所有することで生じる固定資産税や不動産取得税等、税金関係が悩みの種になっています。しかし、現状を見れば農業における土地のやり取りは、貸し借りが大前提になってしまっています。一方で、農地バンク(農地中間管理機構)では、特例事業として農地売買事業が行われていると聞いています。
そこで、農地バンクを活用した特例事業「農地売買事業」の現状について、産業観光部長にお伺いします。
産業観光部長
農地バンクを活用した特例事業「農地売買事業」の現状について、お答えいたします。
耕作放棄地の問題は、本市といたしましても大変危惧しているところです。
この制度につきましては、茨城県農林振興公社が農地中間管理機構(農地バンク)として規模縮小農家等から農地を買入れ、農業者等に農地を売り渡す事業となり、この事業を通じて売買をした場合、譲渡所得税の特別控除(上限800万円)が適用されるほか、必要な事務手続きを茨城県農林振興公社が担うなどのメリット(恩恵)があるもとの認識しているところです。
しかしながら、本事業を活用するためには各種要件があり、一例としましては、売買の対象農地が「農業振興地域内の農用地区域内農地」いわゆる「農振農用地」であることに加え、買入れ者が認定農業者でなければならないなどが挙げられます。
なお、特例事業の本市における直近の実績といたしましては、令和4年度に3件の売買が行われております。
実績として決して多くはありませんが、条件が合致した場合には、本制度に基づき土地を売買することが可能ですので、より広く周知を図ってまいります。
活用のための要件が幾つかあり、まだまだ実績件数が少なくはありますが、農地を売買できる有益な制度ですので、積極的な周知活動を進めていただければ幸いです。
②耕作放棄地解消のための第3セクターを設立する場合の課題
今後の基盤整備事業を円滑に進めるためには、ある程度の規模を持つ農業法人等が土地を手放したい人々の農地をどのように受け入れるかがポイントになります。
そこで本市として第3セクターを新たに立ち上げ、基盤整備事業のための土地の売買を担わせ、不要な土地はほぼ全て引き受けることにしてはいかがでしょうか。そして、この第3セクターがそれら不要な土地を買い取った後に農家に貸し出せば、農家は税金の負担から解放されます。
本市にとっては新たな収入が生まれるメリットがあり、農家は土地が安く手に入り、不要な土地の売り手としては信用のある公的な法人との取引により安心感を得られるため、三方良しになる仕組みと言えます。
なお、基盤整備事業には10年ほどかかるケースもあるため、水田の機能を常に維持していく観点から、第3セクター自身が基盤整備事業の完成までのつなぎ役として耕作を行う必要も出てくるでしょう。
一方、このような第3セクターの設立にあたってのハードルとしては、農地売買の方法が関係法令に抵触しないかという問題等が考えられます。
そこで、関係法令等の問題を含め、耕作放棄地解消のための第3セクターを設立する場合に乗り越えるべき課題について、産業観光部長にお伺いします。
産業観光部長
耕作放棄地解消のための第3セクターを設立する場合の課題について、お答えいたします。
現行の農地法では、取得した「農地」を引き続き「農地」として購入又は賃貸借する場合には、主として農業に従事し耕作することなどの要件を満たすことが求められます。法人の場合も同様で、主たる事業が農業であることのほかにも特定要件が定められておりますので、第3セクターが農地売買可能な法人の資格要件を満たすためには、いくつものハードルを乗り越える必要があります。
例えば、農業経営を行うために、農地法上の農地の権利を所有・取得できる法人となるには「農地所有適格法人」でなければならない訳ですが、事業要件や議決権要件、役員要件など細かく規定されておりますので、それらの要件を全て満たした法人を新たに設立するとなると、当然ですがそれらを実行するための人や予算が必要になることに加え、そもそも当該法人が耕作目的で取得した農地をすぐに売買または賃貸借することはできませんので、実際に農業経営していく上で機械や施設整備、耕作する人員の確保等が必要となります。
そして、第3セクターという公益的な性質上、一般的な法人よりも公平性が求められる上、谷津田など狭隘な農地も取得せざるを得ない状況も考えられることから、その場合の農地の維持費負担や収益を得ることの妥当性など、様々な観点からの協議・検討が必要と考えます。
また、基盤整備事業の観点から申し上げますと、整備エリア内の農地であっても手放したいという所有者がいるのは事実です。しかし、事業要件上、計画に位置づけた担い手へ一定割合(80%以上)を集積・集約する必要があり、仮に第三セクターの体制が整い、整備エリア内の農地を購入した場合に、すぐに他の担い手に貸し付けや売買をすることが農地法上出来ませんので、自らが整備エリア内で営農を行う担い手となるのであれば基盤整備事業の推進は可能かと思います。
そして議員のご意見にあります「つなぎ役」として第3セクターが複数年耕作し、整備エリア内の他の担い手へ貸し出し、将来的に無償で譲渡する案でございますが、複数年の耕作実績があれば貸し付けや売買は農地法上許可される可能性は高いと思われますが、整備エリア内の賃借料関係や借りていた担い手が農地取得を希望しない場合などによって状況が変わるものと考えます。
そのようなことから、ご提案いただいた内容も含め耕作放棄地対策に有効な制度や事業について、さらなる研究・情報の収集に努めてまいりたいと考えております。
ありがとうございました。乗り越えるべき課題が多々あることを理解しました。本市の農地については、農業の担い手の目線に立って、手直しをすべきところを全部直していくくらいの意気込みで取り組まなければなりません。先ほど述べた第3セクター設立がもし実現するならば、耕作放棄地問題の究極の解決策になり得ますので、新しい発想で壁を突破する必要性を改めて感じているところです。
今後もこの問題については、勉強を重ねていく決意を述べまして、次の質問に移ります。
2 高齢者終身サポート事業等について
(1)近親者のいない高齢者単身世帯数
国立社会保障・人口問題研究所の推計によれば、令和32年、西暦でいう2050年には、65歳以上の一人暮らしの割合は、男性26.1%、女性29.3%に上るとされています。我が国の少子高齢化とそれに伴う労働力不足、社会保障費の増大といった社会課題を2050年問題と呼ぶこともあるようです。このような状況下では、近親者のいない高齢者単身世帯が急増することになります。
まずは、本市における近親者のいない高齢者単身世帯の数について、保健福祉部長にお伺いします。
保健福祉部長
近親者のいない高齢者単身世帯数についてお答えいたします。
令和6年度、民生委員による福祉基本調査によりますと、本市の高齢者単身世帯は約1,400世帯で、高齢者と呼ばれる65歳以上の人口のうち約9.5%の方が単身の高齢者となります。
なお、近親者がいるか否かにつきましては、相談があった場合に限り調査しており、すべての単身高齢者についての実態把握はしておりません。
現時点では近親者のいない高齢者単身世帯の数を把握されていないことを理解しました。
(2)近親者のいない高齢者単身世帯への支援
先ほど述べたように、今後10年、20年と経つにつれて、近親者のいない高齢者単身世帯の問題は顕在化していく恐れがあります。
そこで現状を整理するために、近親者のいない高齢者単身世帯への支援について、保健福祉部長にお伺いします。
保健福祉部長
近親者のいない高齢者単身世帯への支援について、お答えいたします。
令和6年度、民生委員による福祉基本調査によりますと、本市の単身高齢者は約1,300人で、議員ご発言のとおり、現在、少子高齢化が進展し、単身高齢者の身元保証や死後事務、日常生活支援などのサービスへのニーズが高まることが見込まれます。
単身高齢者の今後の生活に対する相談や支援策については、長寿福祉課や地域包括支援センターを中心に、関係機関と連携し、その方の生活実態や経済状況を詳細に調査・把握し、その結果により支援方針を決定し、個別に対応をしております。
具体的には、在宅での生活が可能である場合は、在宅介護支援センター職員による訪問をはじめ、緊急通報システムの設置や配食サービスを利用するなど、対象者が住み慣れた地域で安心して生活できるよう支援を行っております。
また、自宅での生活が困難となり施設への入所が必要となった場合は、兄弟や子どもなど近親者等の身辺調査を行い、まずはこの方々に身元引受人や金銭管理、死後事務など支援をいただけるよう依頼いたします。そこで、近親者の支援が得られない場合は成年後見人制度の利用を進めるほか、経済的に困窮している場合は社会福祉課との連携により、施設入所への対応をしております。
今後も、支援が必要となる単身高齢者への相談が見込まれますが、関係機関と連携し、個々の状況に応じた支援に努めてまいりたいと考えております。
現状での支援の状況について理解しました。
(3)本市における高齢者終身サポート事業の実施状況
最近、近親者のいない単身高齢者が入院される場合の身元保証、または、葬儀等を行う際の死後事務が全国的に問題になってきており、それらを包括する「高齢者終身サポート事業」の必要性が指摘されています。現在、様々なニーズを汲んだ高齢者終身サポート事業の事例が全国の市町村で見受けられますので、ここでは二つの具体例を紹介します。
まず、一つ目の例は、福岡市社会福祉協議会の「ずーっとあんしん安らか事業」で、平成23年からスタートしています。対象者は市内に居住する70歳以上で、原則として子供がおらず、生活保護を受けていない等の条件を満たした方です。この事業は、高齢者が入会金1万5千円、年会費1万円を納め、預託金として葬儀等の費用50万円以上、残った家財の処分費用の業者見積額分を生前に納めておく仕組みです。社協側から月2回の電話連絡と3か月に一度の訪問という見守りサービスもついてきます。
次に、二つ目の例として、愛知県知多市のNPO法人「知多地域権利擁護支援センター」の「くらしあんしんサポート事業」が昨年10月から開始されました。対象者は40歳以上で身寄りがなく、生活に不安のある方です。利用者は、まず同センターが運営に協力する「互助会」に入り、月5千円を負担することで、見守り・安否確認や入退院時に緊急連絡先になる等の支援、そして死後事務の請負のサービスが受けられます。
内容をまとめると、死後事務については、今述べた二つの事業のように、生前から預託金や互助会加入の形で月ごとに少額を負担し、あらかじめ金銭的な備えとするのが良いと考えます。
死後事務の問題に限らず、見守りサービスや入退院の支援も含めて、近隣の笠間市社会福祉協議会の「かさま安心サポート事業」等も参考になると思います。
そこで、高齢者終身サポート事業の実施に向けた本市の対応方針を保健福祉部長にお伺いします。
保健福祉部長
高齢者終身サポート事業の実施について、お答えいたします。
この事業は、主に一人暮らしの高齢者等を対象とした、身元保証や日常生活支援、死後事務等に関するサービスを、家族や親族に代わって支援する事業でございます。死後のサービスを含み契約期間が長期であること等の特徴から、利用者の保護の必要性が高く、事業者の適正な運営を確保し、事業の健全な発展を推進するとともに、利用者の安心等を確保していくことが必要となることから、遵守すべき法律等の規定や、留意すべき事項等を関係省庁が横断で整理し、令和6年6月に『高齢者等終身サポート事業者ガイドライン』として策定されました。
本市における本事業への取り組みでございますが、先ほどご答弁いたしました単身高齢者への相談の多くは、身辺調査を行った結果、大半は近親者によって何らかの支援を得ることができているケースとなっており、市におきましては、親族等がおらず、このようなサポート事業を利用できない経済的困窮者への支援が重要であると考えております。県内には民間事業者において同様の事業を行っていることもあり、現段階では、市においてこの事業に取り組む考えはございません。
しかしながら、高齢者の単身世帯の増加や近親者の支援が得られないケースの増加を見据え、市がこの事業を実施する場合の対象者や料金設定、民間事業者との住み分け等も含め、県内外の状況を調査研究してまいりたいと考えております。
ありがとうございました。高齢者終身サポート事業については、今後の本市への影響を考えて今から準備しておくべきであり、国及び県の動向を注視していただければと思います。次の質問に移ります。
3 健康診断のあり方について
(1)本市が実施主体になっている健康診断の法的根拠
昨月市内の各戸に配布された「広報 常陸大宮 お知らせ版 No.547」を読むと、基本健診・がん検診等からなる「集団けんしん」の10月・11月実施分の案内がされていました。我が国ではどこの市町村でも、このような健康診断が実施されていますが、個人の負担金が比較的少額だということもあり、多くの人はありがたい気持ちで健康診断を受けていると思います。
ところが、健康診断について、我が国で常識とされていることが、外国では実は常識ではないということを皆さんご存知でしょうか。例えば、平成31年2月7日付の日本経済新聞によれば、同じ年、国際機関の経済協力開発機構(OECD)は、日本人は健康診断を受ける機会が多いが、本当に費用に見合う効果的なものなのか、項目や頻度を削減する余地はないのか見直すべきだとの提言をまとめています。
これはどういうことかと言えば、一つの診療科のみといった狭い領域で問診や検査を受けるような国はありますが、特に体調が悪いわけでない人も含める形で健康診断を一斉に実施している国は、我が国くらいだと言われています。皆が一律に健康診断を受ける光景は実は世界的には珍しいことなのです。
本市に話を戻しますが、市町村は健康増進法等に基づいて各種健康診断を実施しているかと思います。
そこで、本市が実施主体になっている健康診断の法的根拠について、保健福祉部長にお伺いします。
保健福祉部長
本市が実施主体となっている健康診断の法的根拠について、お答えいたします。
はじめに、現在、市で実施しています健診のうち、40歳から74歳を対象とした特定健診、及び後期高齢者医療広域連合からの委託による75歳以上を対象とした高齢者健診につきましては、高齢者の医療の確保に関する法律に基づき実施しており、中でも特定健診につきましては、法律上、実施が義務づけられている健診となっております。
次に、39歳以下の方や生活保護受給者等を対象とした生活習慣病予防健診のほか、がん検診、肝炎ウイルス検診、骨粗しょう症検診、歯周病検診は、健康増進法に基づき市町村が実施主体となる検診となっております。法律上の位置づけは努力義務となりますが、市町村の責務として積極的に推進するよう努めなければならないと同法第4条により規定されております。さらに、胃がん、肺がん、大腸がん、子宮頸がん、乳がんの5つのがんについては、「がん対策基本法」において、市町村の責務として、がん検診の受診率の向上に資するとともに、がん検診に関する普及啓発その他必要な施策を講ずるもの、と定められております。そのほか、十分な精度が確保された効率の良い検診を実施するために定められた「茨城県がん検診実施指針」に基づき検診を実施しており、検診を実施・推進するために要する費用としまして、がん検診は地方交付税措置、その他の検診は国及び県の補助金が充てられております。
一方、法律に基づかない検診としまして、肝臓、胆のう、膵臓、脾臓、腎臓を検査する腹部超音波検診がございますが、この検診からも毎年がんが発見されております。令和5年第3回市議会定例会の一般質問において、膵臓がんの早期発見を目的とした「尾道方式」についての見解について述べましたとおり、本市における膵臓がんの早期発見のための対策として腹部超音波検診を実施し、40歳以上で検診を希望する方が受診できる検診体制としているところであります。
以上のように、現在実施しています各種健診につきましては、各法律に基づき実施しているものであり、法律に基づかない腹部超音波検診については、市民からの要望が高い膵臓がん等の早期発見のための対策として実施しているものとなっております。
再質問です。健康増進法あるいは厚生労働省令等では、市町村が実施主体となる健康診断の実施項目や実施方法には決まりがあるのでしょうか。保健福祉部長にお伺いします。
保健福祉部長
お答えいたします。
市町村が実施主体となる、法律に基づいた各種健診の実施項目や実施方法については、「特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成19年厚生労働省令第157号)」及び「健康増進事業実施要領」、国及び「茨城県がん検診実施指針」等において定められております。
今ご答弁のあった厚生労働省令や要領・指針等を私も拝読しました。市町村が実施主体となる健康診断の実施項目は、国の方で明確に定めていることが分かります。例えば、厚生労働省令の「特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準」では、第一条「特定健康診査の項目」の中で、「三 身長、体重及び腹囲の検査」、「四 BMI」、「五 血圧の測定」等々、皆様もご存知の健康診断の実施項目が列記されています。
しかしながら、この厚生労働省令には、健康診断の実施方法に関する具体的な記載はなく、他の要領・指針等でも基本的には同様です。ただし、茨城県の定める胃がん、肺がん、大腸がん、乳がん、子宮頸がんの合計五つの「がん検診実施指針」では、集団健診の実施が明記されていることを申し添えます。
再々質問ですが、がん検診を除けば、市町村が実施主体となる健康診断について、集団での実施を義務づける決まりはないと考えて間違いないでしょうか。保健福祉部長に事実関係をお伺いします。
保健福祉部長
お答えいたします。
集団での実施を義務づけているものではありません。
しかしながら、国が示します「標準的な健診・保健指導プログラム」では、各保険者の規模や置かれている状況は様々であることから、適切な外部委託の活用も含め、受診者の利便性やニーズに配慮し、それぞれにあった実施体制を構築して進めることとされており、それに基づき実施しているところです。
集団での実施を義務づける決まりはないものと理解しました。
(2)健康診断の問題点と本市の今後の方針
①健康診断を受けた方のデータ
我が国の医療界からも、現在の健康診断の問題点を指摘する声が徐々に上がってきています。第一の問題点は、健康診断を受けることで死亡率が下がるという明確な証拠が存在しないことです。例えば、欧米では健康診断の効果を検証する臨床試験がいくつも行われています。欧米で健康診断の効果を調べた14の臨床試験の計18万人のデータを解析した論文が平成24年に発表されていますが、健康診断を受けた人と受けなかった人では、全体の死亡率、心臓病、脳卒中、がんによる死亡率に差は見られませんでした。30~60歳の6万人を10年間追跡調査したデンマークの調査でも同じような結果となりました。健康診断を受けたグループは、健康診断に加えて、5年間に4回の健康相談を行い、リスクが高いと判断された人には生活習慣や運動、禁煙のグループ指導も行いましたが、健康診断を受けない人と、心臓病や脳卒中の発症率、全体の死亡率に差がなかったのです。
第二の問題点は、皆が一律に健康診断を受け、年齢・性別を考慮しない基準値をもとに例えば続々とD判定をもらう等して、本来健康な人が通院し、不要な薬を処方されるようなケースが増えていないだろうかという懸念です。具体例を挙げると、健康診断でメタボ症候群に該当する人は、予備軍も含めると令和4年度時点で約1,671万人に上るそうです。これは、メタボ健診の対象となる40~74歳の人口(約5,900万人)の約4人に1人に該当します。この人たちが何十年も薬を飲み続けることになる、そのような社会で良いのでしょうか。
ここで、本市が実施主体になっている健康診断を受けた人のデータについて確認したいと思います。例えば65歳の人が全項目A判定(異常なし)の結果である割合、そして、医療機関を受診すべき目安となるD判定(要精密検査)ないしE判定(要治療)の項目が一つでもある割合は、65歳の人全体から見てそれぞれ何パーセントあるのか、保健福祉部長にお伺いします。
保健福祉部長
健康診断を受けた方のデータについて、お答えいたします。
本市における令和6年度特定健診受診者のうち、65歳の方の結果を見てみますと、「異常なし」は2.5%、医療機関の受診は必要ないが生活習慣の改善が必要とされる「保健指導判定値」は14.9%、「受診勧奨判定値」が一つでもある方の割合は25.6%、既に「治療中」の方は57%でございます。
ありがとうございました。つまりは、このケースで健康診断を受けて問題がなかった人はたったの2.5%だということです。65歳と言えば、昨今では現役で働いている方々も多いわけであって、現行の健康診断の制度ができた時代から年数が経ち、実態と乖離してきてはいないでしょうか。医療技術が年々進歩している我が国において、病人とされる人の数が減らずにどんどん増えていく現状に対し、疑問を持つ動きも徐々に出てきています。
②健康診断の今後の方針
私は健康診断を全て無くしたいとは思いませんが、実施方法の問題を含む健康診断のあり方を少しずつ見直すべきで、そのためには実施主体の一つである市町村からも声を上げていく必要があると考えます。例えば、集団検診のスタイルをやめ、希望者が各自で医療機関に足を運んで健康診断を受け、これにかかったお金を補助するという仕組みに変えていくのも一案です。先ほど(1)での再々質問に対する保健福祉部長ご答弁にもあったとおり、がん検診を除いては、集団で健康診断を実施しなければならない法的な義務はないものと理解しています。
そこで、本市が実施主体になっている健康診断の今後の方針について、鈴木市長にお考えをお伺いします。
保健福祉部長
健康診断の今後の方針について、お答えいたします。
実施方法につきましては、健診の実施主体となる市町村は、国及び県が示す精度管理のもと、市民が受診しやすい体制整備を行うとされており、本市におきましては、特定健診、高齢者健診のほか、胃内視鏡検診、子宮頸がん、乳がん検診において、集団健診のほか医療機関での個別健診も併用した健診体制としているところであります。
議員ご提案の、希望する方が各自医療機関で健診を受診し、その費用を補助するという方法につきましては、市民の主体性を考慮した、新しい切り口の健診方法であると捉えております。しかしながら、令和6年度の体制別受診状況を見ますと、身近な会場で受診できる集団健診を8割を超す方が選択しているという現状があり、一足飛びに医療機関での個別健診のみとすることは、現段階ではハードルが高いものと考えております。
一方で議員ご指摘の通り、健診による医療費の低減あるいは健診と寿命、健康寿命に関するエビデンスは存在しないだけでなく、科学的に検証してみると、効果よりもむしろ擬陽性によって、「無駄な精密検査」「リスクのある処方」「医療費の増加」「不必要な健康不安」といった弊害の方が上回っているとする医師も少なからず存在します。
我が国の場合、健診の判定如何で要精密検査や要治療ということになりますが、外来を受診すれば、薬が処方されるケースが多く、受診勧奨の基準値すなわち健診の判定基準が投薬の基準となる場合もあるという現実もあります。
今後は、広く市民の皆様に医療リテラシー(医療情報を適切に選別し身につける能力)を高めるための様々な情報提供を行い、こと健康に関しては後悔することのない人生を生きて頂けるよう努力していきたいと考えております。そしてその結果として、健診の状況に変化が生じてきた際には、議員提案も含め、しっかりと検討、実施していきたいと考えております。
ありがとうございました。医療の分野に限らず、今後新たな知見が生まれ、当たり前だった基準が変わっていくこともあります。引き続き調査研究いただければ幸いです。次の質問に移ります。
4 東野地内の市道整備について
次に、市道の整備状況についてお伺いします。
(1)東野地内市道20341号線及び市道20306号線の整備の見通し

市道20306号線は、東野地区と鷹巣地区を結ぶ路線であり、国道293号や同118号を使わずに大賀地域に向かう際には便利であるため、私自身、よく利用しています。
ところで、東野に本社及び水戸事業場を置く富士フイルムオプティクス株式会社が、本市の盛金にあった事業場を本年4月に廃止して水戸事業場に統合したため、東野に勤務する方々、ひいては通勤の自家用車等の数が増加しました。
市道20341号線は、県道長沢水戸線から玉川地区センターのT字路を右折して富士フイルムオプティクス株式会社の本社正門及び南側の駐車場等に向かうためのルートになっていますが、大宮町東野1号踏切の箇所を含め、交通量が増えたにもかかわらず、依然として狭隘です。一方、市道20306号線は、逆に鷹巣方面から富士フイルムオプティクス株式会社に向かう場合、センターラインのある片側一車線の路線が途中から幅が狭くなっており、また、お墓のある山の辺りは路面の陥没が複数見られる等、早期の改良が待たれています。
そこで、東野地内市道20341号線及び市道20306号線に対する整備計画の考えと今後の見通しについて、建設部長にお伺いします。
建設部長
東野地内市道20341号線及び市道20306号線の整備の見通しについて、お答えいたします。
富士フイルムオプティクス株式会社の盛金事業場が閉鎖し、東野地内にある水戸事業場に統合されたことに伴い、通勤時の交通量が増えていることは承知しているところでございます。
ご質問の一般県道長沢水戸線から富士フイルムオプティクス株式会社へ進入する市道20341号線については、狭隘で勾配もきつく、道路に近接して建物があり、JRの踏切もございますので、拡幅にはさまざまな課題があると考えております。
次に、鷹巣方面からの市道20306号線については、議員ご指摘のとおり、途中までは整備されており、そこから先は狭隘で、舗装の劣化損傷が激しい箇所もございます。
市としましても、改善の必要性は認識しておりますので、通行の安全や利便性の向上に向けて、優先度や整備の可能性を検討しながら進めてまいりたいと考えております。
課題は多々あるかと思いますが、遠くないうちの本格的な事業化を心から期待し、次に移ります。
(2)東野地内市道21226号線の整備の進捗状況

市道21226号線については、令和6年9月の定例会で私が一般質問を実施していますが、地域住民の関心が高いため、今回改めて取り上げます。
この路線は、東野地内国道293号交差点から八田地区を結ぶ市道であり、その沿線には御陣屋団地(正式名称:グリーンヒルズ大宮・御陣屋)があり、沿線住民は基より東野地区・八田地区における重要な生活道路として、多くの市民の方が利用されています。
しかしながら、起点側国道293号から玉川に架かる御陣屋橋までの約150メートル区間は、道路の幅が狭く、車輌相互通行に支障をきたしています。また、歩道もないことから大宮北小学校や大宮中学校の児童・生徒が通学に利用する際には、通過する車輌と近接し、大変危険な状況となっており、一刻も早い整備を必要とする路線と思われます。
令和6年9月の定例会での一般質問では、昨年度中に道路線形の検討や地形等の測量の実施、さらには地元関係者への説明会を開催する予定とのご答弁がありました。
そこで、東野地内市道21226号線の整備の進捗状況について、建設部長にお伺いします。
建設部長
市道21226号線の整備の進捗について、お答えします。
当路線の国道293号交差点から玉川に架かる御陣屋橋までの約150m区間につきましては、昨年度に地形等の測量を実施し、今年度に入り、警察とも協議を重ねながら道路線形の検討を行ってきたところでございます。ようやく案がまとまりましたので、9月下旬を目標に関係地権者等にお示しし、ご意見を伺う予定でございます。
ありがとうございました。今月下旬という具体的な進捗を知ることができ、ひとまず安堵しました。この市道21226号線については、東野地区及び八田地区の住民から高い関心が寄せられています。早期の整備完了を強く要望し、以上で一般質問を終了します。
以 上